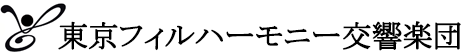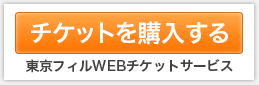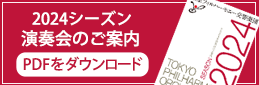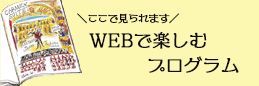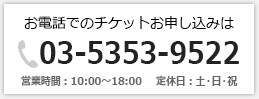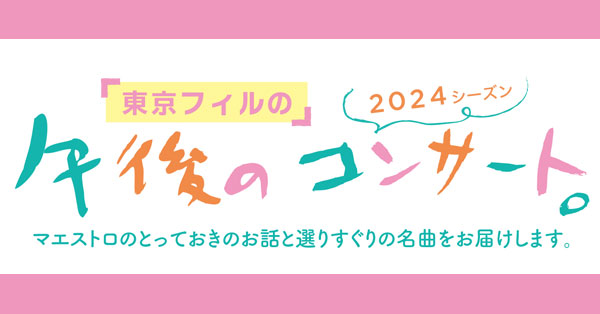インフォメーション
2019年3月14日(木)
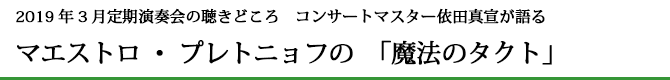
特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフとの共演

©上野隆文
――マエストロ・プレトニョフとの共演についてお尋ねします。マエストロは、どんなリハーサルをなさるのでしょうか?
依田「一言でいえば、“自然体”ですね。ピリピリした空気がまずないし、音楽が自然に流れる、というか。すごく不思議な感覚なのです。(指揮)棒を見てどうこうというよりも、マエストロが自然な流れから出てくるものをこちらに伝えて下さるので、それに沿ってこちらもついていくというか。だから、『ここをこうしましょう、ああしましょう』ということがない。口で、言葉で説明する音楽ではない。だからこちらもストレスなく音楽ができるというか」
――チャイコフスキーもハチャトゥリアンも、たとえば弦楽器のメロディが流れていくときの流れやうねりは非常に印象的です。
依田「空気をもっていますよね。空間を動かすというか、空気を作り出すというか。そこにある音や響きを、マエストロの場合、動かしていくような感じがします。きっと同じプログラムでも、サントリーホール、東京オペラシティ、オーチャードホール、文京シビックホール、と、会場によって全然違う空気感を作り上げて行かれると思います」
初登場、若きヴァイオリニスト、ユーチン・ツェンとの共演

©上野隆文
――初登場のユーチン・ツェンさんとのヴァイオリン協奏曲はいかがですか?
依田「素晴らしいですね。本番はどんどんテンションが上がっていくんだろうな、という感じがします。初日のリハーサルでマエストロの色々なインスピレーションを受けて、どんどん素晴らしい演奏になっていくと思いました。協奏曲というよりは室内楽的というか、アンサンブルの極み、と言うのか、そういう一体感があります」
――マエストロのリハーサルはいつもコンパクトに整理されているように思えます。
依田「そうですね。マエストロの場合、何かを“決める”ことがないんですね。その時その場の、今こういう音楽をやりたい、こういう空間でこういう風に作り上げたい、という感覚で音楽をもっていかれるので。ですからリハーサルでは、もちろんポイントポイントでなにかあったところは修正していますけど、『ここがこうで、あそこがこうで』ということは一切おっっしゃらない。そういう感覚を持ってらっしゃる。それがまたオーケストラだけでなく、聴いているお客様にも伝わるんだと思うんですけれど、不思議な感覚に浸っていただければと思います」
――どんな方に聞いてもマエストロについては“不思議”ということをおっしゃいます。
依田「魔法を使っている、とよく言われますよね。
いろいろな指揮者の方がいますが、空間が分かっても、その動かし方というのは、きっとセンスというか、その方それぞれだと思うのです。マエストロはその空間の動かし方が……完成されていると思うんです。今回ハチャトゥリアンの15本のトランペットの『交響詩曲』は、本当に爆音ですが、その中でもマエストロの空間の作り方、独特のもっていき方、ただ”炸裂している”だけでないということを感じていただけると思います。マエストロならではのスパイスというか、まさに魔法をかける感じです」
――面白いですね。
依田「選曲自体もなかなかやることがないものなので、貴重な機会ですね。マエストロとご一緒できるということも、またひとつ貴重だなと思います。
今回のプログラムに共通する要素として、“祝祭”という言葉が当てはまると思います。“祝祭”という言葉のいろんな意味がこもった、いろいろな“祝祭”感というか。この一言の中に、これだけのいろんな側面があるということを感じていただけると思います。それをオーケストラの響きや音色感を通じて聴いてみていただきたいですね。もちろん演奏者の人数も違いますし、すべての曲の響きが違うと思います」

ハチャトゥリアン『交響詩曲』
サントリー定期演奏会のリハーサルより ©上野隆文
今回のプログラムについて。
――初日のリハーサルが終わった後、マエストロは嬉しそうというか、面白いなぁ、みたいな顔をなさって終わったので、楽しんでらっしゃるなと感じました
依田「マエストロも、プログラムを楽しんでらっしゃるのだろうな、と思います。『交響詩曲』はトランペットが15本もあるので、リハーサルをやっていて“クレイジーだ”とおっしゃっていましたけど。(笑)」
――――以前、マエストロにこの曲についてお話を伺ったとき、日本語で“うるさいよ~”とおっしゃっていました(笑)
依田「確かに、“うるさい”です。(笑)あれだけトランペットの方が並ぶと壮大な景色というか……。どのホールでも、音を出してみないと分からないですが、最初に申し上げたとおり、マエストロがきっと空間をうまく使ってコントロールしてくれる……そのホールに合った音を作り出してくれるんだろうなぁ、と思います。だから、空間を動かす方法が、“魔法”を使って動かす、ということですね」
――やっぱり魔法使いだ……と。
依田「それがまた自然の中でできてしまうのがマエストロです。独特な節回しをすることがあっても、前のパッセージや流れの中でこうしたい、こういうことが起こるから、という意味でやってらっしゃるので、こちらも納得して演奏できる。こう音楽が来ていて、ここをこういう風にすると、次が自然とこういくから、こうしたいんだ、という……。何かをするための辻褄合わせというものを一切しない」
―――なるほど。自然体ですね。それが、あの言葉少ない中でもオーケストラにもはっきり伝わってくるというのは……
依田「それがまた素晴らしいところですし、多分そんなに説明することじゃないのでしょうね。それは素晴らしいことなのだと思うのです。“見たらわかる”というか……ある意味“極み”というか。指揮をやめてしまうこともあります。流れが出来上がって、あえて自分が振る必要がないとか、出来あがったものに対して、指揮者が余計なことをすることはないというか。それで、なにかをしたいときに、ご自身ならではの”スパイス”を加えるというか。」
――“魔法”のステッキを振る。
依田「その一振りが空間を変えてしまうのかもしれません。すごいときはリハーサル演奏中指揮せずにスコアを読んでいるだけのときもあります。本当に、なかなかいないですよね。ああいう方は……」

©上野隆文
マエストロとの音楽には“自由”がある
――マエストロが委ねてくださることで、東京フィルの一体感も同時に感じられるように思います。
依田「そうですね。マエストロは“バトン”をいろんな人にしっかりと渡していきます。そこでまた、演奏の中で信頼関係が生まれてくるというか。ソロの誰かにマエストロが“どうぞ”と委ねると、オーケストラのみなさんが自然に“この人に寄ろう、この人の音楽に空気を寄せていこう”という空気になります。マエストロは全てを網羅された上で、どこがいま大事か、演奏者に任せてくれる。それがオーケストラの自発的な音楽に繋がっていると思います。演奏者は、そのように委ねてもらえると、ただ合わせるだけの音楽ではなく、自分が音楽をやるという形になります。そのことでオーケストラの奏者の音楽性が広がっていくんじゃないかなという感じがします。マエストロとの演奏には自由がある。自由の中で、さらにマエストロが何かを与えて下さる。
本番にならないとわからない部分もいっぱいあり、どの公演も毎公演が楽しみです。演奏する側も皆さんもドキドキというか、どういう本番になるのかという感じですね」
――ありがとうございました。
第918回サントリー定期シリーズ
2019年3月13日[水] 19:00開演(18:30開場)
サントリーホール
第124回東京オペラシティ定期シリーズ
2019年3月15日[金] 19:00開演(18:30開場)
東京オペラシティ コンサートホール
第919回オーチャード定期演奏会
2019年3月21日[木・祝] 15:00開演(14:30開場)
Bunkamura オーチャードホール
響きの森クラシック・シリーズ Vol. 67
2019年3月23日[土] 15:00開演(14:30開場)
文京シビックホール 大ホール
指揮:ミハイル・プレトニョフ(東京フィル特別客演指揮者)
ヴァイオリン:ユーチン・ツェン*
(2015年チャイコフスキー国際コンクール ヴァイオリン部門最高位)
チャイコフスキー/スラヴ行進曲
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲*(3/13,15,21公演のみ除く)
グラズノフ/ヴァイオリン協奏曲*(3/23公演のみ演奏)
ハチャトゥリアン/バレエ音楽『スパルタクス』より“アダージョ”
ハチャトゥリアン/交響曲第3番『交響詩曲』
主催:公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団
助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術創造活動活性化事業)(3/13,15,21)
公益財団法人アフィニス文化財団 ![]() (3/13,15,21)
(3/13,15,21)
協力:Bunkamura(3/21)