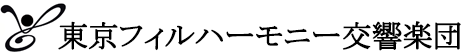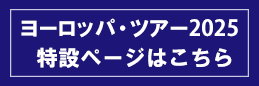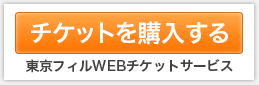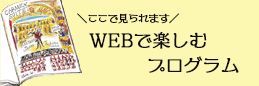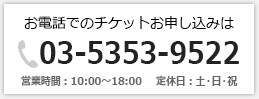インフォメーション
2025年5月12日(月)

プレトニョフ編・ショパン「ピアノ協奏曲第1番」について



2025年5月定期演奏会初日オーチャード定期演奏会より
©上野隆文

5月定期演奏会リハーサルより
今回は、マエストロ プレトニョフの編曲による2曲で、マエストロのテイスト満載の公演です。ショパンはもう言ってしまえばマエストロのショパンというか、マエストロの作品ですね。もちろんソロはショパンの協奏曲のソロですが、オーケストレーションにはもうマエストロの世界観が溢れている、一言それに尽きると思います。(ショパン「第1番」は)私たちも普段から何十回となく弾いてきた作品なのですが、そこで当たり前のように思っているところを“当たり前”で来ない。楽器の音だったり和声感だったり。例えばヴァイオリンが普段弾いている場所で弾かない、逆に、弦楽器ではなく管楽器が演奏しているようなところをヴァイオリンが弾くといった形で、楽器の受け渡しが散りばめられているのです。それでいて演奏効果も高く、もう本当にプレトニョフ・ワールド全開といった感じです。
マエストロがピアニストとして・また指揮者としての観点でショパン「ピアノ協奏曲第1番」について考えておられるヴィジョン、その音楽観、色彩感を『オーケストラと一緒に作り上げるとしたら、こういう風に弾くだろう、弾きたい』そういった気持ちが現れているのだろうと思います。ですから(よくイメージされるような)“コンチェルト”にならないのです。これまでにもマエストロと協奏曲作品でご一緒してきて非常に感じるのは、独奏も含めてオーケストラとのアンサンブルとして捉えていらっしゃること。ソリストとオーケストラが分かれて登場するような感覚があまりないです。ご自身がピアノを弾かれて協奏曲で共演する時も、すべてがつながって、音楽が一つの世界として、その全部がもう一つの線につながっていくように演奏されます。
今回のソリストの松田華音さん、リハーサルではとても緊張したとおっしゃっていましたが、マエストロプレトニョフとご一緒すると、皆さん多分経験する・体験すると思うのですが、自由なようで『ご自由にどうぞ』と突き放す空気ではないというか、大きなところでは導かれているという感覚がいつもするのです。
チャイコフスキー『眠れる森の美女』について

5月定期演奏会リハーサルより

2022年6月定期演奏会より ©K. Miura
リハーサル初日に少しお話しした時に、チャイコフスキーの三大バレエの中でも『眠り』が一番好きだとおっしゃっていて、とてもいろいろな思いがおありのようでした。数年前にマエストロ編の『白鳥の湖』をご一緒にした時とまたちょっと違う印象もあります。これはショパンについてお話ししたこととも通じるかもしれませんが、バレエ音楽ですと、それぞれのキャスト・役柄があって、各場面でダンサーが出てきて、その方のために音楽を作って、我々も弾いて、素晴らしい踊りをご覧いただく。一曲ごとに拍手が生まれたりする。もちろん、バレエではお客様はそれを見にいらしていると思うのですが、今回はそうではない。オーロラ姫、良い妖精・悪い妖精、王子、など、それぞれのキャラクターが音楽の中に存在して、その人たちがどんなふうに踊っているか、どんなシーンであるかということが目の前に浮かぶだけでなく、すべてつながって音楽の中に入っていく。マエストロはその踊りも全部把握した上で、それも含めて一つの音楽絵巻のような感じで作り上げている。曲ごとに音楽が中心にあって、それがあるからこそ次の曲に、という形で一つのストーリーとして繋がっていき、最後にはハッピーエンドとして終わるという、そういう映像を見せられている感じです。バレエの舞台では逆にできない体験ですね。
バレエをお好きな方はもちろん作品をよく知ってお越しになると思うのですが、そこでまた違う世界を見ていただけると思います。バレエの舞台ですと『このシーンが良かった、誰の踊りが良かった』ということが浮かびますし、もちろんバレエはそれがまず醍醐味ですが、今回は総合芸術として音楽で全て世界観を見せてくださいます。以前取り上げた『白鳥の湖』も同様でしたが、今回は今回で、マエストロ自身が『眠り』をとても好きだとおっしゃっている、その愛が非常に溢れている感じがあります。


2025年5月定期演奏会初日オーチャード定期演奏会より
©上野隆文
加えてマエストロの指揮は、そこで和音が“溢れる”感じが独特なのです。完全にマエストロ プレトニョフが出す響きで、仮に同じ楽譜でも他の人には出せないでしょう。テンポ感、出すべき響き、和音の響かせ方、その他すべて、マエストロの指揮を見ていたらわかる。その音になるのです。
今回の版にはヴァイオリンのソロがメインとなる「間奏曲」も組み込まれています。リハーサルで少しお話しされていたのは、この曲はチャイコフスキーにとっては非常に大切なヴァイオリン・ソロだったということでした。マエストロ自身もとても好きな曲とおっしゃっていましたし、ですから、この編曲の中でどこに入れるかはすごく考えておられたそうです。全体としては物語を追っているのですが、演奏される曲の順番は全曲版の順序とはまた違っています。でも、音楽が非常に自然につながるように並べていらっしゃることがわかります。音楽の絵巻を壊さないように、全部つながるように。
リハーサルの手応えは


5月定期演奏会リハーサルより
マエストロ プレトニョフと演奏する時はいつもそうなのですが、もちろんリハーサルでは『こう弾いた』ということを書き込むのですが、でも基本的に書いても次は同じにはなりません。その時にその時に違うんです。だからこそ、今回、3回の本番があって、3回とも全部違うと思います。テンポに関しても、どういうふうに来るか全く想像がつかない。おそらく初日も、リハーサルで弾いたものとも違うでしょうね。毎回そうですが、今回は特に、元の作品を知っている分だけ私たちもそこが楽しみになっています。マエストロはこの作品が全て体に入ってらっしゃる方ですから、全く心配といったことはなくて、単純に最初から最後まで、どういう音楽を今回見せてくださるのかな、という楽しみに尽きます。言ってみれば、同じタイトルの絵本でも日によって読み聞かせの読み方が違う、今日は誰に視点を置いて読んでみよう、今日はここのこの絵をピークに持っていくために、こうやってみようとか、こう読んでみようとか。
私たちは普段仕事として音楽をやるときは、楽譜に指揮者が言ったことを書き込んで、それ自体は必要なことではあるのですが、マエストロのような方とご一緒するときは、もうそこは超越している部分です。『どう振るか』という決め事にこだわりがない方なので、『前からの音楽の流れで、たまたま4つ振りにしていたのが2つ振りになりました』とか、『いつのまにか1つで振っています、最終的に振らなくなりました』とか…(笑)。
前半のショパンに関しても結局そこは共通しているというか、一つの音楽の作品として捉えていて(一般に考えられるような)“コンチェルト”という捉え方ではないですよね。今回のようにご自身で編曲しているものは特に。
ショパンというとピアニストにとってのショーピースみたいなところはありますが、それだけではないショパンの姿を見せていただけるということでしょうか

2025年5月定期演奏会初日オーチャード定期演奏会より
©上野隆文
そうですね。ソロはソロでもちろん、それぞれの個性を発揮する場でもあると思うので、それは大事な要素だと思うのですが、その先の部分ですよね。今回の編曲版は先ほどお話ししたように一つの音楽になっているのですが、ソロが個性を発揮できないかと言われたらそんなことは全くなく、まず音があって、同時にソリストとしての演奏もできて、同時に一体感が生まれているという。だから“魔法”なんでしょうね。マエストロはそれも力技じゃないというところが凄さです。
音楽にはエネルギーはなければならないのですが、エネルギーの出し方ですよね。私たちも、ふだん一所懸命弾いて、それがお客様に伝わって『今日はすごい熱演だったね』と言っていただけることも、もちろんオーケストラの一つの醍醐味というか大切な部分なのですが、マエストロにはそうではない世界があります。オーケストラでも、“力”ではないエネルギーを引き出してくださる、包み込んでくださる、オーケストラの響きを生み出す、そのエネルギーが生まれます。マエストロの音は直線的ではなく、全部丸く包む感じになるのです。

2025年5月定期演奏会初日オーチャード定期演奏会より
©上野隆文
ドバイでのInClassica国際音楽祭では2週間全6公演で異なるプログラム/3人の指揮者のもとでコンサートマスターを務められました。ほぼ初対面の指揮者との短い時間でのリハーサルと本番で質の高い演奏をされていたことについて、現地で実演を聴かれたジャーナリストから賞賛の声がありました。

©InClassica

2週間の滞在で色々なことがありましたが「オーケストラとして、東京フィルとしての音をみんなで作る」という部分で、アンサンブルも含めて、非常に一体感というか、自分たちで音楽を作るということに注力することができた時間だったかもしれないと思います。指揮者が急遽変更になったり、慣れない環境であったりと、いろいろある中で、ある意味では奏者同士それぞれがお互いに阿吽の呼吸や自身が持っている音楽を見せること、そのキャッチボールも含めて、そういうものがきちっとできた時間でした。自分達のアンサンブルを作るという意味では、すごくいい時間だったのかなとは思いますね。集中してあれだけのプログラムを演奏したことで、お互い、どこを指揮者に委ねて、どこを自分たちで作って、というその感覚のバランスの取り具合が、また一つ新しい引き出しとしてできたのかなとは思います。旅先での経験というのは、同じ空間、同じ空気を共有し、アクシデントもある中でも自分たちで音楽を作るというところで、それぞれのセクションがすべきことが非常に明確に出て、それをまた音楽としてみんなで作り上げる時間ができたように思います。
5月定期演奏会
5月11日[日]15:00開演
Bunkamura オーチャードホール
5月13日[火]19:00開演
サントリーホール
5月19日[月]19:00開演
東京オペラシティ コンサートホール
指揮:ミハイル・プレトニョフ
(東京フィル 特別客演指揮者)
ピアノ:松田華音*
ショパン(プレトニョフ編)/ピアノ協奏曲第1番*
チャイコフスキー/バレエ『眠れる森の美女』より(プレトニョフによる特別編集版)
【聴きどころ】特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフは、自身の編曲による大作曲家の作品を2曲取り上げる。ショパンのピアノ協奏曲第1番は、ピアニストとしても超一流のマエストロならではの編曲。オーケスレーションに大幅に手を入れ、独奏ピアノの美しさと妙技を輝かせる。ソリストの松田華音は、6歳でモスクワに渡り、モスクワ音楽院で学んだ若手ピアニスト。ロシア伝統のピアノ奏法を身につけた松田と、マエストロが作り上げるショパンは注目。チャイコフスキーのバレエ音楽『眠れる森の美女』は、プレトニョフ編曲による演奏効果抜群のピアノ独奏版を多くのピアニストが取り上げているが、オーケストラ版が演奏されるのは超レア。マエストロのセンスが光り、作品の新たな魅力発見にもつながるだろう。
文:柴辻純子(音楽評論家)